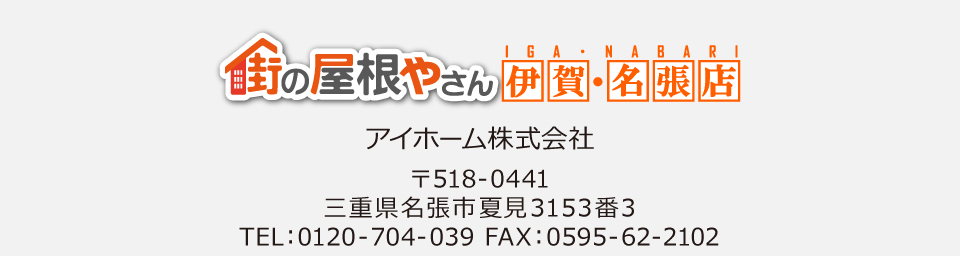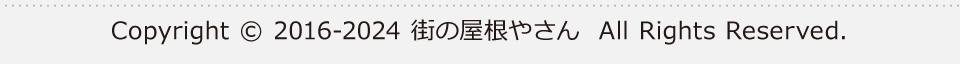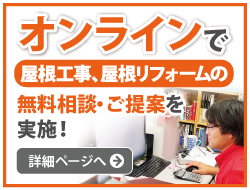

現場を確認すると、大屋根の本棟部分で熨斗(のし)瓦が複数枚割れていました。
熨斗瓦は棟(屋根の頂上部分)を構成する重要な瓦で、ここに割れや欠けが発生すると、そこから雨水が侵入してしまいます。
実際、割れた箇所から雨が入り、付け根に塗られていた白い漆喰がすっかり剥がれ落ちていました。
漆喰は瓦の隙間を埋めて防水や固定の役割を果たしていますが、このまま放置すると中の土が流れ出して棟の形が崩れてしまうこともあります。
このような状態になる前に、早めの補修や積み直しが必要になります。

続いて、本棟の状態を上から確認しました。真上から見ると、下段の熨斗瓦が飛び出して見える部分がありました。
このような棟のズレや歪みは、雨水の侵入によって内部の土が流れているサインです。土台が減ることで瓦が支えられなくなり、時間とともにズレが大きくなっていきます。
今回は、お客様とご相談のうえ、割れている瓦を差し替えて積み直す工事で対応させていただく方向となりました。
もちろん、棟全体を新しく組み直す「棟の葺き替え工事」を行えば、さらに長持ちします。しかし、現状では全交換するほどの損傷ではなかったため、部分的な修復を選択されています。

二階だけでなく、一階の屋根瓦にも劣化が見られました。
陶器瓦の表面が欠けたり、割れたりすることを「はぜる」と呼びます。
今回の現場でも、ところどころでオレンジ色が見える部分がありました。これは内部の素地が露出している証拠です。
陶器瓦は見た目が美しく、耐久性にも優れていますが、内部からはぜていくことが多いため、見た目では気づきにくいことがあります。
特に雨漏りが起きていても、屋内に症状が出るまで時間がかかる場合があるため、定期的な点検が大切です。

下屋(1階の屋根)の点検では、特に袖瓦(屋根の端部分)でのはぜが多く確認できました。
袖瓦は風雨に直接さらされやすいため、他の瓦よりも劣化が進みやすい傾向があります。
今回は、お客様とご相談の結果、割れている部分を中心に瓦の差し替え工事を行うことになりました。
一部葺き替えも検討しましたが、全体的な傷みはまだ軽度だったため、必要な部分のみの補修で十分と判断しています。
陶器瓦がはぜる原因はひとつではありません。
大きな要因としては、経年劣化による水分の吸収と凍結です。瓦は長年のうちに少しずつ水分を含みます。
その水分が冬の寒い時期に凍り、暖かくなると溶ける「凍結と融解」を繰り返すことで、内部に微細なひび割れが生じ、やがて表面が欠けてしまうのです。
特に、伊賀市や名張市のように冬の冷え込みが厳しい地域では、この現象が起きやすくなります。
したがって、寒冷地にお住まいの方は、冬前の屋根点検をおすすめします。瓦の小さな割れや欠けを早めに見つけることで、雨漏りや大掛かりな修繕を防ぐことができます。
今回の現場では、割れた瓦を中心に差し替えを行う予定ですが、今後も年に1回程度の定期点検をおすすめしています。
陶器瓦は長持ちする素材ですが、自然の影響を受けやすい部分もあるため、早めの点検が屋根を守るポイントになります。
屋根の上は普段なかなか見ることができません。
「少し瓦がズレている気がする」「棟の漆喰が落ちてきた」といった小さな異変も、実は雨漏りの前兆かもしれません。
気になる症状があるときは、ぜひ一度ご相談ください。
街の屋根やさん伊賀・名張店では、地域の気候に合わせた最適な屋根メンテナンスをご提案しています。
お問い合わせ先➡『街の屋根やさん伊賀・名張店』
街の屋根やさん伊賀・名張店では、これまで多くのお客様に屋根や外壁の工事をご依頼いただいています。
地域密着だからこそ、一軒一軒丁寧に対応し、安心してお任せいただけるよう心がけています。
工事後には「説明がわかりやすかった」「職人さんが丁寧で安心した」といった嬉しいお声をたくさん頂いています。
初めての工事で不安な方も、実際のお客様の感想を読むことで少し安心していただけると思います。
「こんな対応なら相談してみようかな」と感じていただけたら嬉しいです。
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん伊賀・名張店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.